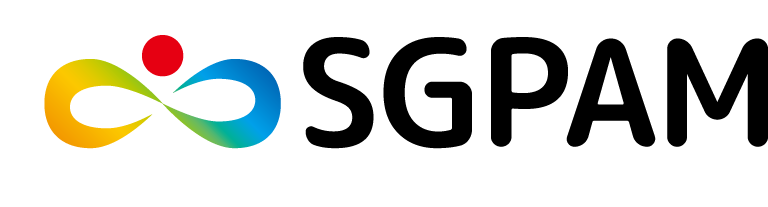この度は、特別例会2023にご参加くださりありがとうございました。
参加後アンケートは 48名の回答をいただきました。アーカイブの再生回数は 398 回でした。以下、各セッションの感想です。
[toc]
目次
症例報告「パーキンソン病患者に鍼灸と共に卓球とムクナ豆は有効か」 ( 金井正博先生:木更津杏林堂/鍼灸師 )に感想ありましたらお聞かせください。
- 地域に卓球の指導者がいらっしゃるので楽しみながら始めようと思います。
- 症例がもう少し多ければ良いと思った
- 鍼灸が有効だということが改めてはっきりと分かりました。 私は毎日30分くらいお灸をしているので、お灸の話をもっと聞きたかったです。
- 勉強になった。
- 鍼灸はまだ経験がありませんが一度試してみたいと考えております。
- 結果に関しては興味深かったですが、サンプル数および観察期間が少ないのでは…と感じました。
- 卓球が有効なのは知っていましたが、鍼灸もその日に受ければ歩きやすくなるという事を知りました。ただ鍼灸と言っても色んなものがあって、どういう鍼灸が良いのかは分からないので教えて欲しいです。
- 歩行テストの動画や卓球をやっているところを見たい。
- わかりやすいお話でした。鍼灸とパーキンソン病との関連が理解できました。
- 有効だということはわかりました。
- 治療に来てくださっている時以外の時にも症状に対して有効な手立てがあり、それをお伝えできるのはとても素晴らしいことだと思いました。卓球はパーキンソン病以外の脳疾患にも有効な気がするので、私もやってみたいです。
- ムクナ豆とピンポンおよび鍼灸の総合的な効果によるパーキンソン病改善の可能性が良く理解できました。
- PDのどの症状に効くのか、もう少し絞り込みが必要。
- 卓球をやろうと思いました。
- 私は今卓球していますのでとても参考になりました。
- パーキンソン病に対して、鍼灸、卓球、ムクナ豆を組み合わせることで効果があるという、貴重な症例を、金井先生が分かりやすくご紹介して頂きました。ありがとうございました。
- 実際の検証で効果が有ることが、わかりやすく示されていた。
- ムクナマメに含まれるL-dopaの血中移行性は良いのかもしれないと期待はあるが、血中動態だけの話なので、なんとも判断しづらい。UPDRSもあまりあてにならないし、評価難しいです。
- 大変参考になりました。
- 私は、この会に初めての参加でしたので、ムクナ豆について、なぜ鍼灸の方々の研究会でセミナーをされるのか、どういう観点から取り組まれているのか、全くわかっておりませんでしたが、ここで何となく分かったような気がします。
- 鍼灸、卓球について、もっと詳しい内容が聞きたかったです。
- 初めて聞く名前の食品であったため、なるほどという感じで視聴させて頂きました。
- 卓球に限らず、体を動かすことが有効なことがよくわかりました。他の運動でも良さそうですが、運動量や手軽さなどの面で卓球が向いているように思えます。
- 大きなテーマに挑戦していただきありがとうございました。卓球のサンプル例がおおまかすぎて?な気がしましたが、興味があるトピックスですので今後もご研究をお願いします。ただいま「抄録」を再度拝見して内容がわかってきました。
- 私たち家族だけでなく、みんなに声をかけて取り入れたいと思いました。
- 面白い組み合わせです。でも具体的に評価するのは難しいですね。
- 1人で卓球のトレーニングができる道具が売られていることがわかり、ありがたかったです。
- 具体的な症例や調理法をあげた説明でとても分かりやすかったです。西洋医学では、どうしても血液検査、造影、投薬というアプローチだけで、実際に体に触れたり体の動きを診たり、日常生活においてどう行動すればいいかという部分まで踏み込む事はないので、何をすれば病気を治せるか、ではなく、何をすれば少しでも楽に毎日を過ごせるか、という観点での卓球とムクナ豆というアプローチも突拍子もないものではなく、効果が見られたと具体的な結果を提示される事で説得力がありました。
症例報告「パーキンソン病の栄養と運動~あなたの体重は大丈夫?~」 ( 山口美佐先生:(社)NSA代表理事/管理栄養士 )に感想ありましたらお聞かせください。
- 体重管理の大切さがよくわかりました。
- とてもわかりやすかった
- 低体重が体に良くないということが分かりました。 食べ物には気をつけて偏りがないように一定の量を食べようと思います。
- 勉強になった。
- 腸活が大事だとつくづく実感しました。しかし、食事がおいしいと感じられず口の中が何かすっきりしない状態が続いておりますのでそれが原因と感じております。
- あらためて体重減少=筋力低下には気を付けたいと思いましたが、栄養学的なことはいままでいろいろ取材してきたこともあり、一般的というか、目新しいことはないな、と感じました。
- メモを取っていたのですが、少し早くてついていけないところがありました。
- 自分が低体重なので、とても興味があった。
- 次回は低体重をテーマにしてほしい。
- 先生ご自身がPDとのことに驚きましたが、前向きな姿勢に感動しました。体重等の自己管理の大切さに改めて気付かされました。
- 今まで体重はあまり気にしていなかったのですが、タンパク質をしっかり摂り、バランスの取れた食事を心がけようと思いました。
- パーキンソン病の患者さんのBMI状態がわかりました。管理栄養士さんの食事指導の仕方がとてもわかりやすかったです。治療にいかしていきたいと思いました。パーキンソン病の患者さんにもっと知ってもらい食事がどれだけ体に影響を及ぼすのかもわかりました。
- 先生ご本人がパーキンソン病と共にいかに快適に元気に過ごすかを勉強されて、それを普及されていらっしゃるお姿に力をいただいた気がします。やはり鍼灸でも胃腸を整えて、低体重をまずなんとかしたいものです。
- ご自身がパーキンソン病患者でもある山口先生の報告は、説得力があり栄養と体重の大切さを自覚しました。ご自身が短距離を走られているのには驚きました。
- プロテインは有効なのか、教えてください。
- ご自身の体験を含めスピーチしてくださり、わかりやすかった。
- ご自身の体調を管理栄養士としてきちんとコントロールされつつ、エビデンス構築のために研究されていて素晴らしいと思います。
- 体重が減少していましたのでバランスを考えます。ありがとうございました。
- パーキンソン病の当事者でもある山口先生の、歩行、ランニング経過写真等、貴重な資料でした。栄養面からは、改めて、どんな栄養素も、適量摂ることが大事だと、感じました。
- ご自身の体験を基に説得力のある講演でした。
- 今後、疾患修飾作用についても検討してくださるとうれしいと思いました。
- 勉強になりました。
- 今回の他の先生方との組み合わせとしてはアンマッチだった気がします。
- よくわかりませんでした。
- バランスの良い食事が大切との事。
- 食事が偏っていると自然と身体が足りないものを食べたいと要求する気がします。
- ただ、この病気になってから、それを作ったり買いに行ったりする時間が限られてしまって、
- 『何でもいいや』になっていると、あらためて気が付きました。
- プレゼン慣れしているいまどきの方の発表で小気味よかったです。内容も昔から言われていることですが、★適度に(PD患者の適度は基礎代謝が大きいので)食事の量をやや多めにとり、多品目種類を摂取するのは大事なことなのだなと実感しました。今回「低体重」を病気だからしかたない、食欲がないからと嘆いてばかりいないで、ロジックに解消する方法があること、低体重の方はぜひ相談すべきだ。とも感じました。ありがとうございました。
- 体重管理が重要だとよく分かりました。
- 具体的な栄養サポートが必要な患者は多いと思います。鍼灸師としてパーキンソン病患者さんをみていても、低体重は薬の効きが悪くなる、便秘になる、転倒しやすくなるというのは本当だと思います。
- 痩せすぎの場合、色々工夫して、標準体重にすることができるのが、よくわかりました。
- 自らが患者であるという事で、講演内容にとても説得力がありました。パーキンソン病に限らず、食事も運動も程度の差はあれど、自分で努力して実行できるものなので、この、「出来る事がある」という感覚を得られるアプローチは生きていく上でとても大事で支えになるなと感じました。
教育講演「パーキンソン病とムクナ豆」(野元 正弘先生:済生会今治病院 臨床研究センター・脳神経内科 センター長)に感想ありましたらお聞かせください。
- パーキンソン病のこと、ムクナ豆のこと、両方の関係性がよくわかりました。
- とてもわかりやすかった
- 私はむくな豆を食べ始めて10年以上になります。 食べ始めた時にこういう話が聞けたら良かったのにと悔やまれます。 薬とむくな豆の量に注意を払わなくてはいけないということを 自覚していなかったので 無計画に食べてしまいました。主治医はむくな豆をやめてくださいという方だったので、 私は「むくな豆はやめません」と答えて主治医からは アドバイスはもらえませんでした。むくな豆を食べ過ぎたような気がします。 薬とむくな豆で エルドーパを取りすぎるとどんな症状が現れるのかが気になります。
- 勉強になった。
- 内容が明快で分かりやすく、勉強になりました。
- ちょっと専門的過ぎて難しかったですが、臨床研究ということで、とても興味深かったです。アーカイブで聞き返してみたいと思います。
- 用語の理解をしていないと難しいなと思われるところもありましたが全般的によくわかりました。
- 内容の濃いご講義でした。8月発行されたという先生の著書も購入予定です。
- 薬とムクナ豆の摂り方がいまひとつわかりませんでした。
- ドパミンの代謝がどのように行われているかわかりました。腸から脳の関係もわかりました。免疫にも関与していることがわかってよかったです。
- この病気について勉強不足で知らないことが多いので、改めて詳しく説明をうかがえて勉強になりました。
- この世界の第一人者である野元先生から直々に、パーキンソン病の昔から現在の最前線の情報が聞けて貴重な時間でした。
- わかりやすかったです。
- パーキンソン病の薬とムクナ豆の効果の違いをグラフでお示しいただいてわかりやすかったです。摂取量についてのご説明も参考になりました。
- むくな豆のことよく知りませんでした。パーキンソンとの関係、まだ理解できません.。
- ありがとうございました。
- 野元先生に、まるでムクナ豆の履歴書を説明して頂いたようで、分かりやすかったです。ムクナ豆を適量摂ることの大切さが伝わってきました。
- PDの成り立ちと薬理作用の詳しい説明をありがとうございます。たいへん勉強になりました。
- 私はPDの進行は、DDCIと3-OMDの蓄積が原因であると思っていました。そのため、DDCIが無く、3-OMDの脳内移行を妨げる「ムクナ豆」でL-DOPAを主に摂取しています。先生のお考えでは3-OMDは害にならないとのことでしたが、長期間の蓄積は障害になる気がします。
- 非常に興味深い内容でした。今後、更にパーキンソン病とムクナ豆の関連性を研究する必要がありそうですね。
- わからないところが多いですね。医師も、ここまで責任を負うようになったら、大変でしょう。
- 勉強になりました。
- 詳しく研究されているなと感心しました。
- 私も、抗パ剤としてのL-ドーパを飲みながら、ムクナ豆の粉末をお茶に溶かして飲んでいるものですが、知りたかったことが理解しやすく助かりました。
- ムクナ豆、期待したいと思い、早速ネットで購入してみました。
- 現実的に効果の度合いなど示していただいたら良かったと思いました。
- 最初から野元先生のお顔がでず残念でした、ご登場前に、パーキンソン病の黒質の部分やお薬の簡単な説明があり、のんきな患者の私にはアーカイブで2回お聴きしてもまだ未だ内容がおぼろげです。それでも野元先生のお話が進むにつれてPDの歴史やいつもどこかで見る資料や全然見たことのない中脳の写真、黒質の茶色のきのこのような物が目を引きました。また「ドパミン神経の作用」の書き方も新鮮でした。いつもドパミンが減るとどうなると言う表現が多く、ドパミン細胞が多いと低血圧になったり、過激な行動、凝り性に。とまであるではありませんか。話は多岐にわたりとてもついていかれなくなりました。Lドパやムクナ豆を粉で服用するか錠剤にするかで細かに効き目の違いのあるデータがでていることをしりました。ありがとうございました。
- コペンハーゲンから情報を届けていただきましてありがとうございました。
- プラシーボ効果でしょうか、先生のお話を聞いて凄く元気になりました。
- 参加者の「これだけは聞きたい」に詳しく答えてくださりありがとうございます。
- 脳神経分野の内容は難しかったのですが、とにかく、神経難病にアプローチする方法として西洋医学の側面ではなく食からのアプローチも有用である事を論理的に数値としても証明されている事により、医療分野の方達の理解が得られやすく、結果、患者にとっても利益に繋がるとても重要な内容だなと感じました。
- 多くの医療スタッフの方に知って欲しい内容でした。
特別講演「ムクナ豆の多様性と食材としての利用法」(三浦 左千夫先生:長崎大学 グローバルヘルス客員教授) に感想ありましたらお聞かせください。
- ムクナ豆を日々の生活に取り入れるヒントをいただきました。
- 参考になった。
- とても理解が進みました
- 薬としてむくな豆を食べているので食材として利用するということはありません。 いろんな食べ方があるのは分かりました。 むくな豆を美味しく食べる方法があるということも分かりました。
- 勉強になった
- パーキンソン病だけではなく、家族に摂食してもらうのも良いのだと、痛感しました。つい
- パーキンソン病の補助薬と考えがちでした。
- ムクナ豆愛に満ちた熱い講演でした。が、私にはどうしてもこの豆、特にきな粉のおいしさが分からず、大好きな果物や料理に振りかけて食べる気持ちにはなりません。きな粉はオブラートに包んで1日一回、あとは、カプセル入りを飲む…。それも、つい飲み忘れてしまうほどです。ムクナ豆の効果を実感できないのも「愛」を感じない理由かもしれませんが。
- ブラジルで長年にわたり栽培されて食事に取り入れられている。素晴らしいですね
- 今年は家で植えていますが凄い勢いで伸びています。収穫が楽しみです。
- ムクナ豆の情報はまだまだ少ないのが現状ですが、栽培方法や具体的なレシピの紹介もあって役立つ情報満載でした。
- ドーパミンを減らさずに食材として利用するにはどうすればいいのかを聞き漏らしました。
- ムクナ豆の可能性がよりわかりました。自分でもっと育ててたくさん収穫したいと思いました。自分でも継続してムクナ豆摂取していきたいと思いました。
- 実際の食べ方、料理の仕方、勉強になりました。
- ムクナ豆を日常の食物の一環として食べている先生の体験談は、ブラジルでの生活談と合わせて大変興味深かった。時間がやや足りなかった感あり、次回以降でのお話も期待しています。
- ムクナ豆に色々な調理法があることを知り面白かったです。パクチーは、患者さんに勧める事もあり参考にします。
- わかりやすかったです。
- ムクナ豆を食べ過ぎると身体に良くない事や、美味しそうな写真に心惹かれました。
- ムクナ豆の食体験のお話は興味深く伺いました。
- 実際食べたくなりました。
- ムクナ豆を食べることの楽しみ、重要性が伝わって来ました。三浦先生の、ブラジルの農場での、ムクナ豆栽培に想いを馳せました。
- 参考になりました。
- 様々な調理法の紹介で、参考になった方も多かったのでは。
- ナラティブに、いろいろご紹介いただき、ありがとうございます。
- 勉強になりました。
- あんなにレシピがあるとはおどろきです。
- 粉末にしたり、熱を加えるほどL-ドーパが減少していくという事を再認識させて頂きました。また、ムクナでではないのですが、バナナは、熱を加える(焼く)とL-ドーパへの食べ合わせの悪さを克服できるという点も参考になりました。
- 食材として色々利用できることがわかり、ハードルが下がりました。試してみようと思います。
- 生活に密着したレポートがわかりやすかったです。
- ムクナ豆がこれほどとは。
- 生活に豆をもっとということも考えました。
- ムクナ豆の栄養価を改めて認識しました。
- 先生自身やブラジルの豆料理事情、ムクナ豆の実践的利用法を見させていただき、ブラジルの人々の深いパワーの素の一部を知りました。学食にまでムクナパウダーや、焼きバナナなど栄養のバランスを考えられているのは勿論、常識なんですね。各種データの見方やムクナ豆摂取の実例など興味深くアーカイブで何度も見させていただきました。ムクナ豆を薬の代用ではなく、(主治医からは許可済み)健康食の趣で先生の失敗談も忘れずにとってみようかなと思い始めました。ありがとうございました。
- 海外ではムクナ豆が生活に生かされている地域がある事がよく分かりました。
- 「ムクナ豆とL-dopa」は「天然塩と精製塩」の関係で考えるととても分かりやすいですね。ムクナ豆を長時間煮こんでL-dopaは少なくなっても、繊維質があるからお通じに良いし、抗炎症作用、抗酸化作用や免疫など多彩な働きがあり健康に役立ちますね。酢ムクナに挑戦したいと思います。
- ムクナ豆の全体像を細かく説明してくださり、またそのきな粉を日常の食事にどんな風に取り入れているのか、魅力的な写真と共にご紹介があり、楽しく拝見しました。
- ムクナ豆という食品をつい最近知ったので、身近ではないナゾの豆に、ドーパミン神経を刺激する力がある事を知り驚きました。豆の存在がもっとポピュラーになれば、パーキンソンだからという理由だけでなく、栄養素としても取りやすくなっていいなと思い、流通ルートが広がるといいなと感じつつ、摂取の仕方にも注意が必要な面は化学薬剤と同じなので薬剤師の方々にも漢方薬の様な存在としてもっと存在と知識が広まって薬局で相談できる様な大切が整うといいなと感じました。
総合討論 に感想ありましたらお聞かせください。
- わかりやすい言葉ですぐお答えしていただきよくわかりました。
- とても理解が進みました
- とても勉強になりました。
- まとめとしてわかりやすかった
- α-シヌクレインについてもっとお聞きしたかった。
- ムクナ豆に関しての効能、可能性についてはとても興味を覚えましたが、今購入しているものが果たして正規のムクナ豆なのかどうか、はたまた、どのくらいの量を摂ればいいのか、
- L-ドーパの含有量が3-7%って?目安にならないし、薬じゃないからこそ、指標があると助かるなあ(個々のケースによって違うので難しいでしょうが…)、と思いました。というのも、以前、更年期の取材をしていたとき、外国からイソフラボンのサプリを取り寄せて飲んでいる人が、その効果が強すぎて、怖くなってやめてしまった…という話を聞いたことがあったので。
- 冒頭の写真説明の部分でまさかのPCフリーズ、退室し入り直したのですが時すでに遅し、説明ができず大変に失礼してしまいました。せっかくお時間を頂いて、しかも前日から張り切って準備していたのに本当に悔しく申し訳ない思いです。代わりに説明をしてくださりありがとうございました。
- パーキンソン病、腸内細菌、ムクナ豆が繋がり、もともと日本種の豆がパーキンソン病だけでなくいろいろな病気から身を守る助けになるかもしれない可能性を知り、世界が広がりました。
- 一般の方には、やや難しく感じるのかもと思いました。
- 全体として、エビデンスとなる定量評価が少ないかな、と感じました。
- 盛りだくさんで参考になる内容がたくさんありました。シヌクレインの凝集についても勉強になりました。
- 先生方やり取りを聞き、つながっておられることがよくわかりました。資料の信頼性よくわかりましたありがとうございました。
- いろいろな質問に、各々、先生方がお答え頂き、内容の濃いものでした。ムクナ豆の成分には、パーキンソン病に効果が有り、免疫力をアップして、ガン細胞をやっつける効果も、、、と明るい光の見えるお話し、嬉しいです。
- 短い時間内でも有益な討論会でした。
- わからないことが前提での議論でしたので、、、どうすればいいのでしょうね。
- 勉強になりました。
- パーキンソン病のもはやバイブルです。
- やはり、L-ドーパの含有量について、確認するのが難しく、容易に測定できるものでは
- 無さそうなのが残念です。私は、抗パ薬の量が多かった時期に、ひどい症状になり、ムクナに置き換えて凌いでおりますが、これも飲み過ぎるのが怖くてその含有量について、敏感になっております。ムクナ食材や粉末等に表示できない。薬事法何かしらの目安を設けるか、統一した企画範囲内を設けて、服用量の参考になる、L-ドーパ含有量のコントロールする方法または流通体制は出来ないか。本格的に出来ないものでしょうかね?
- 前述の通りですが、データや数字を示して頂けたらより参考になります。
- お一人お一人の先生からの、想い、視点などからの総合討論は、パーキンソン病研究とその患者への熱い思いが感じ取れ、素晴らしい会でした。
- 薬ではなく、自然な食品から、生活の中から、身体が改善の方向に行けることがあれば、薬の体への負担も軽くなることも
- 人権をも守ることにも繋がることだと思います。
- 東洋、西洋、それ以前に生活からも、人の健康寿命、幸せ寿命を守れるように、と願います。
- たいへん充実したお話を伺うことが出来、先生方のご研究に感謝致します。
- 質問に対して専門の先生方が、即お答えしていただいたので分かりやすかったです。
- 中谷先生や藤井先生のコメントは、もっと詳しくお伺いしたい内容でしたが、時間の関係で泣く泣く短くしてもらいました。もったいなかったけれど贅沢な綜合討論でありました。
- ムクナに関するエキスパートな方達の討論で、情報があまりにも多すぎて何度か動画を見返しました。とても貴重な時間でした。西洋医学、鍼灸、管理栄養士と職務のカテゴリーを越えた立場の方達、それぞれの意見を聞ける機会はないので、否定するのではなく理解していこうという姿勢の方達がいる、と知れるだけでも、相談できる相手を見つけるのが難しい難病患者にはとても嬉しい光景でした。